~なぜ、こんな話を?誰もが知る文豪が終結。異色のミステリーアンソロジー~
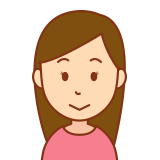
こんにちはくまりすです。今回は日本文学史に名を残す文豪たちのアンソロジー『文豪たちの妙な話』をご紹介いたします。
story:
夏目漱石、森鴎外、芥川龍之介、梶井基次郎、佐藤春夫、谷崎潤一郎、久米正雄、太宰治、横光利一、正宗白鳥ら日本文学史に名を残す10人の文豪が書いた「妙な話」を集めたアンソロジー。病院で聞いた「変な音」、突如消えた時計など日常に潜む謎から、盗みや殺人をしてしまう犯罪心理まで、「人間の心の不思議」に迫る異色のミステリー。(「BOOK」データベースより)
変な音 夏目 漱石
story:病気で入院していた主人公がある夜変な物音で目が覚めた。耳を澄ませてみるとどうやら隣の病室から聞こえるらしい。その音はまるでおろし金を擦っているような奇妙な物音だった。不思議に思いながらも退院と共にそのことへの関心は薄れていった主人公だが、再入院した病室は例の部屋の西隣だと気づき…。
7ページの短編。夏目漱石のホラーかと思わせるような設定です。
「夜の病院」「変な音」もうそれだけで怖い。読みやすくページも短いのでさらっと読めます。
ちょうど夏目漱石が大病を患って入院した後に発表されたとのことで、主人公は夏目漱石本人であり、これはその実体験をもとに書かれたものという話も。
この小説は大学入試センター試験にも出題されたため、ネット検索をするといろんな考察が見られます。生死観や孤独について云々、構成や手法が云々。しかし、私はそういう事を考えて読むとあまり楽しめないので、難しいことは抜きにして純粋にミステリーとして楽しみました。
1867-1916。江戸牛込馬場下(現在の新宿区喜久井町)に生れる。帝国大学英文科卒。松山中学、五高等で英語を教え、英国に留学した。留学中は極度の神経症に悩まされたという。帰国後、一高、東大で教鞭をとる。1905(明治38)年、「吾輩は猫である」を発表し大評判となる。翌年には「坊っちゃん」「草枕」など次々と話題作を発表。’07年、東大を辞し、新聞社に入社して創作に専念。『三四郎』『それから』『行人』『こころ』等、日本文学史に輝く数々の傑作を著した。最後の大作『明暗』執筆中に胃潰瘍が悪化し永眠。享年50(「BOOK」データベースより)
カズイスチカ 森 鴎外
story:医学士の花房が開業医の父を手伝い、幾人かの患者を受け持った時の話。まだ、国民が医学の知識が乏しかった時代、患者の家族はその病名が分からず花房に必死で症状を訴えるのだが、なんとも不思議な症状でー。
約20ページの短編。『分身』に収められ出版されました。
情報が限られていた時代、家族や知人に見聞きしたこともない病気の症状が出た時の驚きと不安は想像を絶するものでしょう。あわてて医者に行き患者の症状を説明するのですが、その説明がなんとも要領が得ない例えで面白い。「倅が一枚板になった」なんて言われてもなんのこっちゃですよね。
軍医としても活躍した森先生の医学知識を生かした物語でした。
1862-1922。本名・森林太郎。石見国鹿足郡津和野町に生れる。東大医学部卒業後、陸軍軍医に。1884(明治17)年から4年間ドイツへ留学。帰国後、留学中に交際していたドイツ女性との悲恋を基に処女小説「舞姫」を執筆。以後、軍人としては軍医総監へと昇進するが、内面では伝統的な家父長制と自我との矛盾に悩み、多数の小説・随想を発表する。近代日本文学を代表する作家の一人(「BOOK」データベースより)
妙な話 芥川 龍之介
story:ある冬の日、私は旧友から彼の妹・千枝子が体験した不思議な出来事を聞いた。それは、彼女がよく会う不気味な赤帽の男の話だった。
千枝子が会ったその赤帽の男は、突然千枝子に戦争に行っているはずの彼女の夫の消息を訪ねてきた。そして、夫からの手紙が届かなくなったことに不安を抱いていた彼女に「私が旦那様にお目にかかって参りましょう」と言ったという。その後、再び彼女の前に現れた赤帽はわかるはずのない夫の近況を彼女に伝えてきて…。
約10ページの短編。
芥川の奇妙な話といえば『妖婆』を思い出しますが、あれはどちらかと言えばホラーのカテゴリーに入るのでしょうか。この話もちょっとホラーテイスト。赤帽の顔が覚えられなかったり、雨や風車といった小技が効いている。怪談話を聞いているようなぞわぞわ感とそれでどうなるの?と思わせる筋運びは流石です。
この奇妙な話を最後三行で、全く別の話にしてしまうのが芥川らしいところ。ちょっと薄気味悪いねと思ってたのに真顔になってしまったよ。物の怪と捉えるか皮肉と捉えるか、解釈を読者に委ねる感じです。結局真実は藪の中なのか。
明治25(1892)年東京生まれ。東大在学中に豊島与志雄や菊池寛らと第三次「新思潮」を発刊。大正5(1916)年に発表した「鼻」が夏目漱石に激賞され、続く「芋粥」「手巾」も好評を博す。後年は、厭世的人生観に拠った作品を手がけ、また小説の「筋」をめぐり谷崎潤一郎との文学論争に至った。昭和2(1927)年、「ぼんやりした不安」から睡眠薬自殺。遺稿は「歯車」「或阿呆の一生」など(「BOOK」データベースより)
関連ブログ☛芥川追想
Kの昇天ーあるいはKの溺死 梶井 基次郎
story:影と『ドッペルゲンゲル』。私はこの二つに、月夜になれば憑かれるんですよ。満月の夜、療養で訪れた土地の砂浜で私はK君と出会ったー。
K君の溺死を知った私が、Kとの出会いから一緒に過ごした1ヵ月間の出来事を書簡体形式で綴っています。死の真相の考察はミステリー要素もある作品。
人気の高い短編で、梶井基次郎自身のドッペルゲンガー体験をもとに描かれたとのこと。 神秘的空想の世界を描いた 幻想小説とされる一方、ミステリーとしての側面もあると評されています。
まるで夢の中にいるかのように幻想的で詩的なのですが、ちょっとつかみづらかったところも。『檸檬』を読んだときにも感じましたが、風景の描写がどこかこの世ではない世界に迷い込んだような感覚になるのです。
明治34年、大阪に生まれる。東京帝国大学文学部中退。東大在学中の大正14年に同人誌『青空』を創刊、「檸檬」を発表。以後、同人誌を中心に「城のある町にて」「桜の樹の下には」などの詩的作品を発表し続けた。昭和7年、肺結核のため、31歳の若さで逝去(「BOOK」データベースより)
時計のいたずら 佐藤 春夫
story:主人公の男は思い入れのある時計を失くしてしまった。確か二階の部屋のいつもの場所に置いていたはずなのに誰か持ち去ったのだろうか?あの晩、家に3人の客がいた…いや、ちょっと待てこの窓は確か…
約30ページの短編。
江戸川乱歩が「最も純粋探偵小説に近い作品を書いている」と評する佐藤春夫。主人公が時計を失くしたということに端を発して彼らの推理が始まる展開はれっきとした探偵小説でしょう。とは言え、主人公はダメダメで全く役に立たない上、記憶もおぼろげなので、読者は推理出来ない。彼らをあたたかく見守りながら読み終えた。
1892(明治25)年和歌山県東牟婁郡新宮町(現・新宮市)に生まれる。1910年上京後、与謝野寛・生田長江に師事。また永井荷風に学び、慶應義塾大学在籍中から「スバル」「三田文学」で詩歌と評論に早熟の才を示した。1918(大正7)年、谷崎潤一郎の推挙により文壇に登場。青春の憂愁を詠う『田園の憂鬱』や、探偵小説『指紋』、ユートピア小説『美しき町』など、洒脱なロマンに独自の作風を示し、新進流行作家となった。1935(昭和10)年より芥川賞の初代選考委員を務め、戦中・戦後にわたって長く文壇で重きをなした。著作は、詩歌から小説、戯曲、評伝、童話など多岐にわたる。1964年死去(「BOOK」データベースより)
私 谷崎 潤一郎
story:私が一高の寄宿寮にいた時の回想。友人と集まった時、最近寮によく泥棒が出るという話になった。泥棒は私が持っている「下り藤の紋付」を着ていたらしく、私と仲がうまくいっていない平田は私を疑うような視線をよこす。私は、疑われていることについて触れないのも不自然だが、聞かれていないのに否定するのも怪しいと自分の中で葛藤するが…
約20ページの短編。私にとっては初谷崎潤一郎の作品です。
これは純文学にミステリーの要素が含まれていると言った感じで面白かった。初めは、とても考えさせられる話だと思っていたのに裏切られたような気持に。驚きと面白さと後味の悪さと。
この頃の谷崎潤一郎の作風の傾向は…とか、○○トリックだとか、ちょっと検索するとすぐネタバレが出てくるので、先入観なしでさっと読むことをお勧めします。
谷崎潤一郎(タニザキジュンイチロウ)
明治19(1886)年、東京・日本橋生まれ。東京帝国大学国文科中退。明治43(1910)年「新思潮」を創刊、「刺青」「麒麟」を発表する。永井荷風に激賞され、一躍文壇の寵児に。西欧崇拝から日本古来の美へと指向は変化しつつ、ゆるぎない美意識に貫かれた作品を生涯にわたり発表し続けた。昭和24(1949)年、文化勲章受章。昭和39(1964)年、日本人として初めて米国文学芸術アカデミー名誉会員に選ばれる。昭和40(1965)年7月に逝去(「BOOK」データベースより)
復讐 久米 正雄
story:大学生の高田は、下宿している部屋から見下ろせる平屋の住人が何度も入れ替わることが気になっていた。新しく住人が越して来るたびに興味を持ってその家族を観察するなどしていた。
どの住人も長くは居つかなかったその家に、ある日、若い綺麗な奥さんが越してきた。言葉を交わすうちに好意を抱くようになった高田の目には彼女もまんざらでもないように映ったのだが…
久米正雄の学生時代を題材にした初期短編集『学生時代』に収められている作品。約20ページの短編。
久米の初期の頃の作品は純文学ど真ん中というものが多かったので、ミステリー仕立てのこの作品は新鮮で驚きました。ミステリー風な作品ちゃんと書けるのにどうしてこういう作品が少ないんだろう。面白く、一気に読みましたが、結末は男女では違う感想になるかもね。いや、素直に言うと性格悪!!って言うね…。でも、そういうところも好きです。
1981-1952。長野県に生まれる。一高・東大で菊池寛、芥川龍之介らと出会い、同人誌で競い合う。学生時代に戯曲『牛乳屋の兄弟』が話題になる。代表作に『受験生の手記』『虎』など(「BOOK」データベースより)
関連ブログ☛久米正雄作品集
日の出前 太宰 治
story:昭和の初め、ある高名な洋画家一家に起こった異常な事件。
洋画家の息子・勝治は中学卒業後の進路について、思い描いていた夢が父に受け入れられなかった。次第に荒れていく勝治に家族は戸惑いながらも更生を信じていた。しかし、悪い仲間ができ、そのうち家族の物を勝手に質屋に持って行くようになり…
約30ページの短編。
実際にあった事件をもとに書かれた作品で、昭和十七年の発表当時は「戦時下において内容が不適切である」とのことで全文削除になったようです。
以前読んだ『斜陽』にもどうしようもないクズ人間や悪人が出てくるのですが、この作品の勝治や友人もそのどうしようもない人たちです。亭主関白な父親や主張しない母親など、その時代は当たり前だった家族像も今にして思えば、どこかいびつですね。風刺がきいていていて面白かったけれど、太宰自身もどちらかというと勝治側の人間では?彼はどんな心境でこの作品を書いたのだろうと考えてしまいました。
1909年、青森県金木村(現五所川原市)生まれ。東京大学仏文科在学中に非合法運動に従事するもやがて転向、本格的な執筆活動に入る。35年「逆行」が第1回芥川賞の次席となり、翌年、第一創作集『晩年』を刊行。39年に結婚し「富嶽百景」「女生徒」「ろまん燈籠」など多くの佳作を執筆。戦後、『斜陽』でベストセラー作家になるが、「人間失格」を発表した48年に玉川上水で入水自殺をはかり死去(「BOOK」データベースより)
マルクスの審判 横光 利一
story:踏切で事故が起きないようにするために踏切の番人という仕事がある。ある時、踏切の番人の男がそこにいるのにもかかわらず、酔漢が轢死したという事件が起こった。予審判事はその踏切の番人の男の審判を行うが、彼の言動から不自然さを感じ、疑いを持つ。判事は疑いを確証するためにさらに質問を重ねるが…
約30ページの短編。
この作品は、志賀直哉の『范の犯罪』、芥川龍之介の『薮の中』に影響を受けて執筆したようです。
轢死が故意か過失かという所がこの裁判の争点。判事はこの問題を即物的に見ようとするが、そうすればするほど主観的に考えてしまい、誘導尋問まで行う始末。しかし、その返答に対してもさらに疑問を持つという…。この判事の独り相撲のような感じが面白い。疑問がループしている判事に大丈夫かと言ってやりたくなりました。
1898年〈明治31年〉3月17日 – 1947年〈昭和22年〉12月30日)日本の小説家・俳人・評論家である。本名は横光利一(よこみつ としかず)菊池寛に師事し、川端康成と共に新感覚派として大正から昭和にかけて活躍した。『日輪』と『蠅』で鮮烈なデビューを果たし、『機械』は日本のモダニズム文学の頂点とも絶賛され、また形式主義文学論争を展開し『純粋小説論』を発表するなど評論活動も行い、長編『旅愁』では西洋と東洋の文明の対立について書くなど多彩な表現を行った。(ウィキペディア(Wikipedia)より)
人を殺したが… 正宗 白鳥
story:保はかつて関係のあったとき子が未亡人になった事を知り、金銭目的もあって彼女の家に行くが、彼女の義理の弟と鉢合わせをしてうっかり殺してしまう。しかし、職もなく母や弟から邪魔者扱いされていた保は自分には人を殺せる隠れた力があるのだという自負をもち…
200ページ弱の中編。
白鳥が初めて週刊誌に連載することになった小説。当時、探偵小説が流行った背景もあり、江戸川乱歩を意識した作品とも言われています。
始めは正常だった人間が次第に精神異常者のようになっていく過程がリアル。正常と異常の境界線がどこだか分からないし、主人公の妄想や思い込みに読んでいるこちらまでおかしくなってしまいそうだった。主人公のサイコパス的な一面と臆病な性格を併せ持った狂気が恐ろしくも悲しくもあります。現代のミステリー小説にも通じる面白さでした。
1879・3・3~1962・10・28。小説家。岡山県生まれ。東京専門学校(早稲田大学の前身)文学科卒。キリスト教に惹かれ受洗、内村鑑三に感化される。後に棄教の態度を示すが、生涯、聖書を尊重した。1903年、読売新聞社に入社、7年間、美術、文芸、演劇の記事を担当、辛辣な批評で名を馳せる。『紅塵』(07年)、『何処へ』(08年)を刊行するや、代表的自然主義作家として遇される。劇作も多く試み、評論でも重きをなした(「BOOK」データベースより)
1956年、北海道生まれ。推理小説研究家。ミステリー評論家の新保博久との共編著『幻影の蔵 江戸川乱歩探偵小説蔵書目録』で2003年に日本推理作家協会賞(評論その他の部門)受賞。数多くの文庫解説の執筆、アンソロジーの編纂に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)


