~「ふと、この芽を摘んでしまおうか、という残酷な思いがわき起こる」人間誰しもが持つ、光と影の輝き~
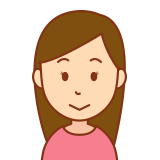
こんにちは、くまりすです。今回は直木賞受賞作品、窪美澄「夜に星を放つ」をご紹介いたします。
story:
かけがえのない人間関係を失い傷ついた者たちが、再び誰かと心を通わせることができるのかを問いかける短編集。
コロナ禍のさなか、婚活アプリで出会った恋人との関係、30歳を前に早世した双子の妹の彼氏との交流を通して、人が人と別れることの哀しみを描く「真夜中のアボカド」。学校でいじめを受けている女子中学生と亡くなった母親の幽霊との奇妙な同居生活を描く「真珠星スピカ」、父の再婚相手との微妙な溝を埋められない小学生の寄る辺なさを描く「星の随に」など、人の心の揺らぎが輝きを放つ五編。(「BOOK」データーベースより)
アボガド
コロナ禍のステイホームで人と会えず、なんとなく体と心が弱っていた綾はアボガドの種を捨てようとして、ふと思った。「これ、植えたら育つんじゃないの?」
綾は芽が出ることを期待してアボガドを育てるが、なかなか変化が起こらない。
そんなある日、綾は婚活アプリで出会った麻生さんに自身が大切にしている秘密を打ち明ける。秘密を共有したことで麻生さんをより身近に感じた綾に対して、麻生さんは何かを言おうとして口ごもる。麻生さんの秘密も知りたいと思う綾だが…。(「真夜中のアボガド」より)
ステイホームのコロナ禍でなかなか人と会えなかった人も多いですよね。特にリモートワークだと毎日の変化もあまりなく、日々が過ぎ去っていく気がします。そういう時、何かちょっとした変化でもあるとうれしいもの。
仕事をしているデスクの目に入るところに私はアボガドの種の入ったグラスを置いた。なんとなくアボガドに監視されているみたいだな、と思いながら。けれど、その頃の私にはそういうものが必要だったのだ。眼に見えて育っていくかもしれない命の元みたいな存在が。
植物は癒されますね。ただ、植物が人の代わりになるかというとそれは難しいでしょう。
ひとりでいると人恋しくなる時があります。そして、独身の女性ならたとえコロナ禍であったとしても恋をしたいと思うはず。
しかし、仕事が忙しいと言われ、麻生さんに会えない日が続きます。
ふとテーブルの上に目をやると、グラスの中のアボガドからは双葉のようなものが伸びている。いつの間に…。毎日水を替えていたが、最近はそれが二日に一回になり…(中略)私が麻生さんから来ないLINEを待っていたり、髪の毛をショートにしている間に、アボガドは素知らぬ顔で育っていた。なんだか、アボガドが憎らしかった。人の気も知らずに…。ふと、この芽を摘んでしまおうか、という残酷な思いがわき起こる。(後略)
こういった綾の気持ちがなんとなく分からなくもないですね。
鬱屈した気持ちを抱えていた綾はアボガドの芽を摘もうとしますが…。

麻生さんと村瀬君
コロナ禍での自粛生活が続く中でも綾には会いたいと思う男性が二人いる。一人は婚活アプリで知り合った麻生さん。そしてもう一人は妹・弓ちゃんの彼氏だった村瀬君。
「寝てたでしょう?」
無表情で村瀬君が言う。いつものことだ。
「いや、うとうとしてただけ」
「元気だった?」
「まあまあ」
「婚活は?」
「ぼちぼち」
綾と気さくに話が出来る村瀬君。義理の弟になるはずだった村瀬君は綾にとって大切な存在です。
例え血のつながりがなくても、家族になるであろう人は特別なはず。自粛生活で孤独を感じている時に、まず会いたいと思うのは気の置けない人だと言うのは分かりますが、でも、それだけでしょうか?
LINEのやりとりは続いているが、麻生さんからの返信はまるで間欠泉のよう。来たり来なかったり。最後のメッセージは一月の終わりで恒例の「今、仕事が忙しくてごめん!落ち着いたら連絡します」で止まっていた。(中略)もう、こんなことが続くなら、また、違う人にした方がいいのかな…。
結婚を前提にお付き合いをしている麻生さんはどうやら今は仕事が忙しいとのこと。なかなか会えない彼に不安は募りつつも、見込みがなければ次に行こうという割り切った気持ちもある綾。女心は複雑ですね。何もこんなコロナ禍で無理をして相手を見つけなくても良いのでは?とも思いますが、綾には早く結婚したいと思う理由があったのです。
そんなある日、綾は偶然にも麻生さんと同じ電車に乗り合わせますが…。
感想
「貝殻をひろうように、身をかがめて言葉をひろえ」
これは著者の窪美澄が「いつもそうでありたい」と思っている詩の一節。
それを知って、腑に落ちた。まさにこの小説には貝殻のような、星屑のような詩的な言葉や表現の数々が散りばめられていました。
「(前略)左側の車窓いっぱいに海が見える。僕は思わずシートから腰を浮かし、窓に鼻をくっつけて海だけを視界のなかに入れていたくなる。」
「僕の足元だけがあたたかな泥のぬかるみに浸っているのだ。」
その光景がすっと目に浮かぶような表現の中に彼らの感情も伝わってきて物語の世界に入り込んでしまいます。また、文章は簡潔で読みやすく、登場人物の心情を豊かに表現したエッセイを読んでいる感覚にもなりました。
アプリの婚活やテレワークといったまさに“今”の日常を描いているそれぞれの物語は、コロナ禍で希薄になった人間関係の大切さを再認識させてくれます。
家族や恋人といった関係の絆が一番強いと思われがちですが、そういった身近な人間関係に縛られずに、もっと範囲を広げたら手を差し伸べてくれる人が沢山いる。人と接することで心が軽くなることもある。
「コロナ禍のなんとなく気落ちする世の中に、明るい光を差すような優しい物語を書こうと思って、この本ができました。」と、著者は小説を書いた理由をこう語りました。
大切な人を失ったり、うまくいかない関係に悩まされたり。人間関係でつらい思いをしても、それでも人恋しい。人と繋がっていたい。明日への一歩を踏み出せる、人にやさしくなれる物語です。
1965年東京都生まれ。2009年「ミクマリ」で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した『ふがいない僕は空を見た』が、本の雑誌が選ぶ2010年度ベスト10第1位、2011年本屋大賞第2位に選ばれる。また同年、同書で山本周五郎賞を受賞。12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データーベースより)
関連書籍👇
前回の直木賞1:『黒牢城』米澤 穂信
ミステリー作家、米澤穂信の直木賞受賞作品。各ミステリー賞でも6冠を達成しています。
荒木村重が籠城する有岡城内で人質、自念が死んだ。自決かと思われたその死体にはなんと矢傷があり、その部屋は密室状態だった。村重の家臣たちの動揺を鎮めようと、その時に自念の部屋を見張っていた家臣から証言を取るも誰も犯行を行うことは不可能だと思われた。行き詰った村重は地下の牢に閉じ込めた黒田官兵衛の知恵を借りようとするのだが…
この物語は、織田信長に反旗を翻した村重が籠城した有岡城内で起こったミステリーを描いている。科学的な解決法は皆無なこの時代、探偵小説さながらに官兵衛、村重の冴えわたる推理が展開されます。
また、籠城の緊迫感のなか起こる事件は、人々の心に疑心暗鬼を植え付け、さらに次の事件の引き金に。追い詰められていく有岡城と村重、そして家臣たちとの関係の変化などが複雑に絡み合い、衝撃の結末へ向かって物語が動いていく。
ミステリの精髄と歴史小説の王道、歴史ミステリーの面白さを詰め込んだ一冊。
前回の直木賞2:『塞王の楯』今村 翔吾
吉川英治文学新人賞や、山田風太郎賞など数々の賞を受賞している今村翔吾の2022年直木賞受賞作品。
戦国時代、穴太衆と呼ばれる石垣職人集団と鉄砲職人集団の国友衆の戦いを描いた物語。
穴太衆は質の高い技術をもって堅牢な石垣を作ることで有名であった。方や国友衆は城を難なく落とせるほど優れた鉄砲を創る日本一の技術を持っていた。
最強の楯と矛がぶつかったらどちらが勝つのか?運命の対決に職人の魂とプライドをかけた戦いが幕を開ける。
この物語のクライマックスは2人の天才職人の対決ですが、そこに至るまでの石垣職人匡介の成長や友情を描いた人間ドラマも見どころです。厳しい職人の世界、石垣の積み方や加工なども知ることが出来て面白い。
関ヶ原の前哨戦とも位置付けられる大津城の戦いの場面は一進一退の攻防に胸が熱くなります。
この小説を読む前はただの石に見えた石垣もその奥深さを知った後では、まったく違って見えます。
手に汗握る時代小説。

