~マスコミには決して書けないことがある――心に残るゴースト・ストーリー~
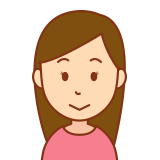
こんにちはくまりすです。今回は直木賞候補作品・高野和明『踏切の幽霊』をご紹介いたします。
story:
マスコミには、決して書けないことがあるー都会の片隅にある踏切で撮影された、一枚の心霊写真。同じ踏切では、列車の非常停止が相次いでいた。雑誌記者の松田は、読者からの投稿をもとに心霊ネタの取材に乗り出すが、やがて彼の調査は幽霊事件にまつわる思わぬ真実に辿り着く。1994年冬、東京・下北沢で起こった怪異の全貌を描き、読む者に慄くような感動をもたらす幽霊小説の決定版!(「BOOK」データベースより)
幽霊
今やすっかり夏の風物詩となった怪談話。怖がりながらも、ついつい耳を傾けてしまいます。
死者の存在が怖いのは勿論の事ですが、何よりもその霊の未練や恨みなどの怨念は身の危険を感じる恐ろしさがあります。一方で、生前親しかった人であれば、幽霊でもいいからもう一度会いたいと思う事も。情のあるなしで感情が大きく異なりますね。自身から遠く離れた正体不明の人物程、恐ろしく感じるものなのかも知れません。
「心霊ネタ?」
契約更新まであと2か月と迫ったある日、フリーの記者である松田は編集長の井沢に呼ばれ、心霊現象の取材を依頼されます。専門外の案件でしたが、このところ失敗続きの松田に断れるはずもなく、ここが踏ん張りどころと引き受けることに。
手始めにと読者から送られてきた8ミリ映像を見る松田。そこに映っていたのは…
ズームで寄った映像は、多少の手ぶれがあるものの、明瞭に踏切を捉えていた。画面奥のカーブから列車が現れたタイミングで、踏切の中に何かぼんやりしたものが浮かび上がり、蒸気のように揺らめいてから、ほんの数秒で消えた。(中略)
松田は拍子抜けした。「何ですか、今のは?」
「幽霊だよ」と井沢が断じた。
薄気味悪いですね。しかし、霊の存在を信じていない松田は肩透かしを食らったようで、何かしらの不具合ではないかと勘ぐるばかり。
「そうか?だがな、これには続きがあるんだ」
(中略)
写真に目をやった松田は、かすかな寒気を覚えた。画面の手前に写っているのは、高齢の婦人と孫娘らしい少女、そして二人の足下でお座りをしている子犬だ。もう一人、すぐ後ろの踏切上に、まるで通行人が偶然に写り込んだかのように横向きの女性の姿があるが、その人物は…(中略)
記者としての習性で、その印象を言い表す一語を探した松田は、あらためてぞっとした。写真の背後に浮いている女は、『死者』だった。(後略)
仕事柄、様々な人を見てきた経験から被写体がこの世の人ではないと直感した松田。ふと、この案件には前任者がいたことを思い出し…

感想
実を言うと、この物語はホラー小説ではなく、幽霊話に端を発したミステリー。話の中心はあくまで事件の謎ですが、恐怖を煽る描写がとても雰囲気があり、それがどんどん実態を伴ってくる怖さは、幽霊話が得意ではない私の読書習慣を夜から朝に変えるのに十分でした。
物語の舞台は1994年、今から約30年前のお話。この年は、大手新聞社の発行部数が1000万部の大台に乗った年であり、雑誌もピーク目前で、まさに出版物の隆盛期。バブル崩壊後とはいえ、まだサラリーマンがバリバリ働くことが普通の時代。記者である主人公や、彼を取り巻く人々の労働観や人生観は競争社会における懐かしい仕事風景を思い起こさせます。
膨れ上がった人口による街の活気と人々の愛憎、古いものから新しいものへと移っていく過渡期の不安定な空気。今とは比べ物にならないくらい様々な感情や欲が渦巻き、見過ごされた社会の闇も多かったはず。この時代背景により霊の念もより強く悲しいものに印象付けられました。
また、足で情報を稼ぐ取材ならではの証拠の積み重ねが丁寧に描かれ、事件の真相に迫る緊迫感や高揚感がリアル。人の体温を感じられます。一方で、ミステリーとゴーストの組み合わせは新しく、ファンタジーのような一面も。
重厚なストーリーですが、とても読みやすく豊かな感情を味わえます。時代を超えた新しいミステリーでした。
1964年生まれ。映画監督・岡本喜八氏に師事し、映画・テレビの撮影スタッフを経て脚本家、小説家に。2001年『13階段』で江戸川乱歩賞を、2011年の『ジェノサイド』で山田風太郎賞と日本推理作家協会賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

