~あの災厄から十年余り、男はその地を彷徨いつづけた。~
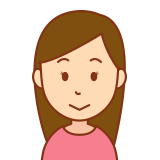
こんにちはくまりすです。今回は芥川賞受賞作品・佐藤厚志の『荒地の家族』をご紹介いたします。
story:
元の生活に戻りたいと人が言う時の「元」とはいつの時点かーー。40歳の植木職人・坂井祐治は、あの災厄の二年後に妻を病気で喪い、仕事道具もさらわれ苦しい日々を過ごす。地元の友人も、くすぶった境遇には変わりない。誰もが何かを失い、元の生活には決して戻らない。仙台在住の書店員作家が描く、止むことのない渇きと痛み。(出版社より)
災厄
あれから10年以上が経った今も多くの爪痕を残している東日本大震災。毎年3月になると思い出したようにニュースやドキュメンタリーなどの特集が放映されますが、TVから流れるのはあの日のショッキングな映像と、この10年の復興の軌跡ばかりが目立ちます。道路や防潮堤などのインフラは整備され、避難所生活者も減少傾向。見た目には復興が着実に進んでいるように感じられます。しかし、真の復興とはその土地に暮らす人々の心の中にあるのではないでしょうか。
浜を囲んでいた松林もすっきりと消えた海岸では、サーファーを見かける以外、カイトをあげて遊ぶ親子も、酒を飲んで騒ぐ大学生も、犬を連れて散歩する人の姿もない。たまたま閑散とした浜を目にしただけなのに、人が地上から消え失せたような気がした。祐治は光を帯びて凪ぐ海を見つめた。沖が膨らんで、海面が上昇する。海水があふれて押し寄せてくる。そして静かに元に戻る。祐治は、隙あらば人をたらふく飲み込もうと手ぐすねを引く化け物が一時の眠りについているという空想に耽った。
「波が来た」と言うよりも海面全体が盛り上がったように見えた。そういう証言は多くあったそうで、「沖が膨らむ」と言う表現はその時の恐怖が込められた生々しさを感じます。
主人公の祐治は仕事に精を出す毎日ですが、ふと目にした復興の景色にもあの日の出来事を連想し、畏怖の念を抱かずにはいられません。また、その町の人々もおそらく祐治と同じような気持ちだと思わせる風景ですね。虚しさや喪失感がこの町を覆っている気がします。
元の生活に戻りたいと人が言う時の「元」とはいつの時点か、と祐治は思う。十年前か。二十年前か。一人ひとりの「元」はそれぞれ時代も場所も違い、一番平穏だった感情を取り戻したいと願う。
至る所で町の風景は刻々と変化しています。しかし、人が新しく作る変化と、失くしたものを補おうとする復興はまた違うようです。新しい建物や道路が出来ても昔の記憶を呼び起こす手がかりになる建造物は一切ない。そう思う祐治。一緒につるんでいた友達との思い出や、子供から大人へと成長していった日々の歴史をどこにも見つけられず、感じられない。復興の景色は全く知らない新しい町であり、故郷を失った現実を目の前に突き付けられているようにも思われる。あの出来事を体験していない自分に戻れるのならどんなにいいだろうか。そんな祐治の心の叫びが聞こえてきそうです。

復興
しかし、祐治は立ち止まっているわけではありません。がむしゃらに働き、未来に目を向けます。知加子と出会い、新しい生活を始めた祐治ですが…。
食器は全て、まるで引っ越しの準備のように新聞紙でくるまれていた。開く前から嫌な予感がしたが、案の定、中の器は全て粉々に割られていた。ただ割ったというのではなく、執拗に砕かれていた。それで祐治は知加子が出て行ったと理解した。
なにもかもが裏目に出てしまう現実に呆然とする祐治。あの手この手で知加子本人の口から出て行った理由を聞こうとします。
一方で、植木職人の祐治は一人親方として仕事に精を出していました。そんなある日、仕事のため訪れた家で懐かしい顔を見かけます。
どうも、と祐治は声をかけたが、男は無視をして家に入っていった。挨拶は耳に届いているのに、しかめた顔をうつむき加減にして、わざとこちらを見ないようにしている印象だった。
あっけにとられていると、六郎が「息子の明夫だ」と言った。
ああ、やっぱりそう、と祐治は言った。
顔見知りのはずの明夫に無視をされ祐治は驚きます。
「明夫の車見たべ、あいな車さ乗ってるやつがら誰が車買うんだ、おめ」
中古車販売の仕事をしているという明夫ですが、彼の乗って来た車は下品に改造されたもの。六郎の軽口に大笑いする祐治。しかし、しばらく会わない間に明夫に一体何があったのでしょうか。祐治は明夫と話をするために彼の会社を訪れますが…。
感想
「3月11日じゃないと届けられない気持ち」フィギュアスケート選手の羽生結弦さんは3月11日を含む3日間、地元の宮城県でアイスショーの開催を予定している。自身も被災者だからこそ復興への強い願いがあるのだとか。
被災した方々はもとより、全ての日本国民が忘れることの出来ない災厄。あの日の記憶はストレスやトラウマとして心の奥底に残り、今でも震災関連のキーワードを見るだけで憂鬱になる人も多いのではないでしょうか。
この物語で描かれているのは震災後の人々の日常や人間模様。彼らの目線の先には常に震災の風景が広がっています。
著者の佐藤厚志は「震災を書かなければいけないとか、義務感のようなことはなくて、宮城県で日常を小説にするときに、風景として震災が入ってくるのは自然なことなので、どこか癒しがあればいいかなという思いで書いた」とその理由を語っています。
とは言え、登場人物の抱えている問題に震災が起因しているわけではありません。ただ、ふとした時に忍び寄る無力感や停滞感を感じる描写から被災者の渇きがリアルに伝わってきます。心の奥に沈殿している「しこり」は彼らと同じ目線でその風景を見て初めてわかるもので、ニュースや新聞などが伝える復興とはかけ離れたものでした。
一方で、そんな中でも前を向こうとする祐治の姿は人間の底力、自然と共生してきた日本人の特有の自然観も感じられます。また、祐治のさまざまな行動や言動も人とのつながりの大切さを身にしみて感じているからこそだと言えるでしょう。
「私の中には2つの時計があります。一つは震災の時に止まった時計、もう一つは今を刻んでいる時計です」ある記事でこんな被災者の声を目にしました。家族を亡くしたことによって止まったままの時計と、忙しい毎日に追われる時計の2つがあるのだそうです。目には見えない「心の復興」はまだまだ時間が必要であり、そんな人々がいることを私たちは知らなければいけないと思います。
1982年宮城県仙台市生まれ。東北学院大学文学部英文学科卒業。仙台市在住、丸善 仙台アエル店勤務。2017年第49回新潮新人賞を「蛇沼」で受賞。2020年第3回仙台短編文学賞大賞を「境界の円居(まどい)」で受賞。2021年「象の皮膚」が第34回三島由紀夫賞候補。2023年「荒地の家族」で第168回芥川龍之介賞を受賞。これまでの著作に『象の皮膚』(新潮社刊)がある。(新潮社HP 著者プロフィールより)
こちらもおすすめ👇
芥川賞同時受賞作品:『この世の喜びよ』井戸川 射子
story:幼い娘たちとよく一緒に過ごしたショッピングセンター。喪服売り場で働く「あなた」は、フードコートの常連の少女と知り合う。かつての子育ての日々を思い出す女性ー「この世の喜びよ」。ハウスメーカーの建売住宅にひとり体験宿泊する主婦ー「マイホーム」。父子連れのキャンプに叔父と参加した少年ー「キャンプ」。(「BOOK」データベースより)
読書ブログはコチラ☛『この世の喜びよ』井戸川射子

