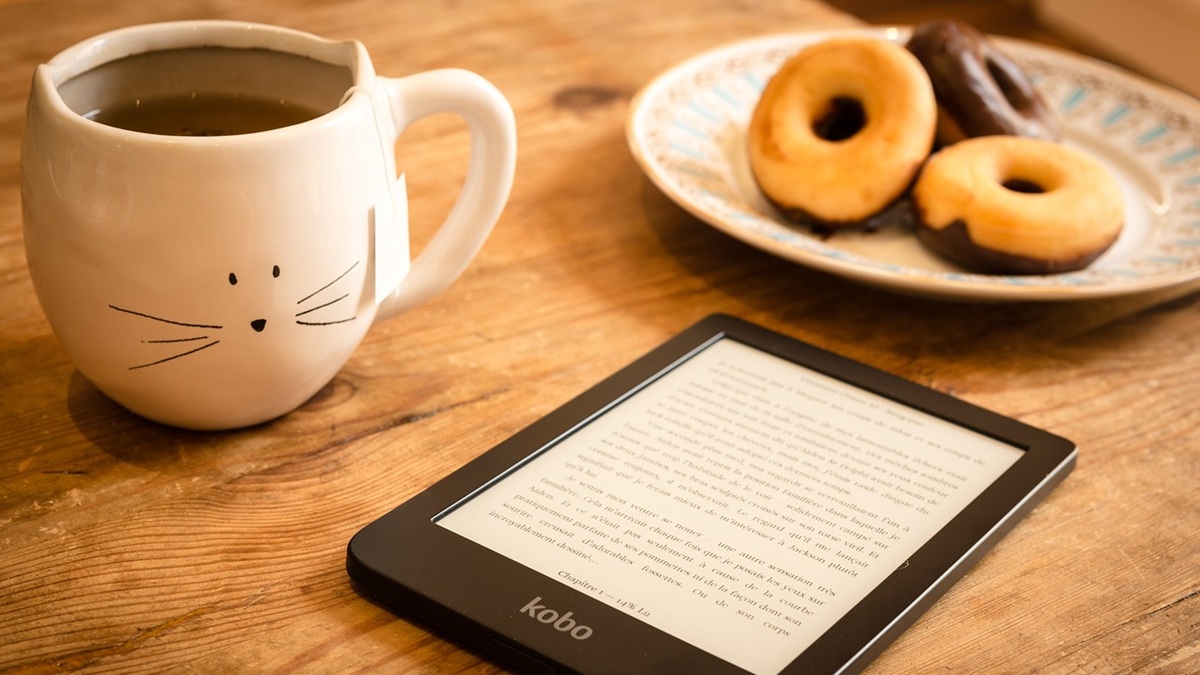2025年7月・8月に読んだ本をまとめました。
人気作家さん、話題の本を中心に読んでいます。
私の満足度・おススメ度で★をつけています。
★★★★★ とても良かった!!人に薦めたい!これを読まないなんて、人生損している!
★★★★ とても良かった!充実した時間をありがとう。是非、読んでみてください!!
★★★ 読んで良かった。面白かったです。読んで損はない!
★★ 少し難しかったかな?あなたの意見を聞かせてください。
★ う~ん、今の私には難解だった。また、再挑戦します。
あくまで私の基準です。本選びの参考になればうれしいです。
愛じゃないならこれは何 斜線堂 有紀
★★★★★
斜線堂有紀さんのはじめての恋愛小説短編集。「2025年集英社ナツイチ」対象文庫。
story:赤羽瑠璃のアイドル人生、そして地獄へ続く恋のはじまりは、4年前。たった一つのファンのツイートだった。(「ミニカーだって一生推してろ」)。28歳の誕生日。10年来の想い人から贈られたガラスの靴に浮かれるファッションデザイナー・灰羽妃楽姫は直後、その彼からまさかの結婚報告を受けー(「きみの長靴でいいです」)。恋する彼女たちは愚かで滑稽で、なお愛おしい。文庫書き下ろしを含む全6編。(「BOOK」データベースより)
甘い愛、大人の愛、切ない愛。定番ジャンルとして人気のある恋愛小説はたくさんあります。その中には偏執的な愛の形も数多く描かれているわけですが、ドロドロとしていたり、重かったりと意外と読者を選ぶテーマなのも事実です。しかし、よく考えてみれば、「愛」という感情は理性では説明がつかないもの。できるものならなりふり構わず「愛」を成就させたいと願うのも当たり前の事ではないでしょうか。
この短編集は、言葉では説明がつかないけれども、誰もが「わかる」を感じられるユーモアたっぷりで読みやすい恋愛小説。
湧き上がる感情に抗えず愛を追いかける一方、そんな自身に対してどこかシニカルな見方をしている自分もいる。粘度の高い愛をカラッとした表現で描くことにより、人間のアブノーマルな部分を面白がりながらも「わかる」と共感できてしまい、心に刺さります。
恋している人は勿論、恋愛小説が苦手な人でも楽しめる一冊です。
1993年秋田県生まれ。2016年『キネマ探偵カレイドミステリー』で第23回電撃小説大賞〈メディアワークス文庫賞〉を受賞しデビュー。24年『星が人を愛すことなかれ』で第4回本屋が選ぶ大人の恋愛小説大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)
夏の庭 -THE FRIENDS- 湯本 香樹実
★★★★★
日本児童文学者協会新人賞や、アメリカの児童文学賞であるボストングローブ・ホーンブック賞、ミルドレッド・バチェルダー賞など受賞多数。世界十数か国で翻訳出版されている湯本香樹実さんのベストセラー小説。「2025年新潮文庫の100冊」対象小説。
story:町外れに暮らすひとりの老人をぼくらは「観察」し始めた。生ける屍のような老人が死ぬ瞬間をこの目で見るために。夏休みを迎え、ぼくらの好奇心は日ごと高まるけれど、不思議と老人は元気になっていくようだー。いつしか少年たちの「観察」は、老人との深い交流へと姿を変え始めていたのだが…。喪われ逝くものと、決して失われぬものとに触れた少年たちを描く清新な物語。(「BOOK」データベースより)
「私は、あの12歳の時に持った友人に勝る友人を、その後、二度と持ったことはない。誰でも、そうなのではないだろうか」死体探しの旅に出るという少年たちのかけがえのないひと夏を描いた『スタンド・バイ・ミー』は小説・映画共、不朽の名作として今なお多くの人の心に感動を与え続けています。
子供は小学生くらいの年齢になると、死について強い好奇心を持ち、詳しいことを知りたがるそうです。そんな時、多くは親や周りの大人が動植物などの世話をしながら子供の心に寄り添い、命の大切さを教えていくことになります。
しかし、物語の主人公とその友達は家庭環境に問題があり、その機会に恵まれません。そして、わんぱくな少年たちの好奇心は目の前に現れた「死を体現してくれるであろう老人」に注がれることに…。
懐かしい「あの頃」を思い出させてくれる冒険心。わくわくが詰まった子供の純粋な世界と無味乾燥で複雑な大人社会。子供の視点で描かれる物語は、大人になるにつれて徐々に失われれていく真っ直ぐな強さや生きることに対する真剣さを思い出せてくれ、そして目に見えない大切なものへの気づきに涙しました。
「この世界には隠れているもの、見えないものがいっぱいあるんだろう。」
読みやすく、大人から子供まで楽しめる児童文学。爽やかな読後感の名作です。
1959年東京都生まれ。作家。1993年『夏の庭ーThe Friends-』で、日本児童文学者協会新人賞、児童文芸新人賞を受賞。本作品は10カ国以上で翻訳され、ボストン・グローブ=ホーン・ブック賞、ミルドレッド・バチェルダー賞などを受賞。2009年『くまとやまねこ』(絵:酒井駒子)で講談社出版文化賞絵本賞を受賞。本作品はフランスやパレスチナなど、10の国と地域で翻訳される。絵本の翻訳も手がける(「BOOK」データベースより)
海の見える理髪店 荻原 浩
★★★★★
荻原浩さんの直木賞受賞作品。2022年にテレビドラマ化されました。「2025年集英社ナツイチ」対象文庫。
story:店主の腕に惚れて、有名俳優や政財界の大物が通いつめたという伝説の理髪店。僕はある想いを胸に、予約をいれて海辺の店を訪れるが…「海の見える理髪店」。独自の美意識を押し付ける画家の母から逃れて十六年。弟に促され実家に戻った私が見た母は…「いつか来た道」。人生に訪れる喪失と向き合い、希望を見出す人々を描く全6編。父と息子、母と娘など、儚く愛おしい家族小説集。直木賞受賞作。(「BOOK」データベースより)
『海の見える理髪店』はじんわりと心に沁みる家族の短編物語集です。
平凡な家族であったり、反対に機能不全家族であったり。それぞれ描かれている家庭環境は様々ですが、いずれもありきたりな日常の特別な一コマが切なく温かい。人生の酸いも甘いも経験した大人の現実的で擦れた捉え方をする主人公達。決して理想的ではないリアルな人物像に、読者はどこか自嘲めいた共感を感じながら、いつかの自身の姿を重ねるかも知れません。
軽妙な文章の中に味わい深いフレーズが散りばめられており、すらすらと読めるのにしっかりと残る余韻があります。苦い思い出の奥にあるうま味を感じられる、成熟した大人たちに捧げられる人生の味を噛みしめる一冊です。
1956年埼玉県生まれ。広告制作会社勤務を経て、コピーライターとして独立。97年『オロロ畑でつかまえて』で小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。2005年『明日の記憶』で山本周五郎賞、14年『二千七百の夏と冬』で山田風太郎賞、16年『海の見える理髪店』で直木賞、24年『笑う森』で中央公論文芸賞を受賞(本データは2025年2月現在のものです)(「BOOK」データベースより)
月と六ペンス サマセット・モーム
サマセット・モームの歴史的大ベストセラー。画家のポール・ゴーギャンをモデルにした伝記風小説。「2025年新潮文庫の100冊」対象小説。
story:ある夕食会で出会った、冴えない男ストリックランド。ロンドンで、仕事、家庭と何不自由ない暮らしを送っていた彼がある日、忽然と行方をくらませたという。パリで再会した彼の口から真相を聞いたとき、私は耳を疑った。四十をすぎた男が、すべてを捨てて挑んだこととはー。ある天才画家の情熱の生涯を描き、正気と狂気が混在する人間の本質に迫る、歴史的大ベストセラーの新訳。(「BOOK」データベースより)
英国の文豪サマセット・モームは、作家業の他に英国諜報機関MI6のスパイとして活動していたことでも知られている異色の作家なんだそうです。そう言われてみれば、登場人物の際立った個性の描写に観察眼の鋭さを感じたり、会話の駆け引きの見事さに著者の勘の良さが見えたり。終始、うっすらと漂う緊張感も相まって、フィナーレへの期待が高まっていくストーリーは、読者を惹きつけて離さない面白さがありました。
また、軽快に交わされるブラックジョークを交えた会話は辛辣でありながらクスッとさせられるイギリス流知的ユーモアが満載。一人の男の姿を通して、人間の価値観の違いや、幸せな生き方の哲学を堅苦しくなく楽しめ、考えさせられます。
難しい言葉はなく、読みやすい文章とエンタメ性のあるストーリーで、今も読み継がれている名作。悔いのない人生を送ろうと思わせられる一冊です。
1874-1965。イギリスの小説家・劇作家。フランスのパリに生れるが、幼くして両親を亡くし、南イングランドの叔父のもとで育つ。ドイツのハイデルベルク大学、ロンドンの聖トマス病院付属医学校で学ぶ。医療助手の経験を描いた小説『ランベスのライザ』(1897)が注目され、作家生活に入る。1919年に発表した『月と六ペンス』は空前のベストセラーとなった代表作である(「BOOK」データベースより)
ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ
★★★★★
今秋、公開予定の映画「ミーツ・ザ・ワールド」原作小説。「2025年集英社ナツイチ」対象文庫。
story:焼肉擬人化漫画をこよなく愛する腐女子の由嘉里。恋愛経験ゼロで、人生二度目の合コンも失敗した帰り、新宿歌舞伎町で美しいキャバ嬢・ライと出会う。「私はこの世界から消えなきゃいけない」と語るライに、「生きてなきゃだめです」と詰め寄る由嘉里。正反対の二人は一緒に暮らすことになってー。世間の常識を軽やかに飛び越え、新たな世界の扉を開く傑作長編。第35回柴田錬三郎賞受賞作。(「BOOK」データベースより)
「リア充」という言葉が一般的に使われるようになった理由は、反対に生活が人並みに充実していない「非リア充」だと自覚している人が多数いるからなんだとか。多様化社会において自分らしい生き方を推奨されているものの、無意識のうちに強いられる「普通の幸せ」にストレスを抱えている人も多いのではないでしょうか。
物語の主人公・由嘉里は、現実の男性よりも二次元の男性キャラクターにときめく腐女子。彼女は容姿や社交性に自信がなく、現実社会ではうまくいかないことが多々あると感じている一人です。そんな由嘉里へ向けた登場人物たちの言葉には、様々な生きづらさを抱えている現代人へ向けた力強いメッセージが沢山。今を幸せに生きるためのヒントが散りばめられています。
また、随所に差し込まれる由嘉里による生粋のオタクトーク面白く、焼肉擬人化BLに対する熱量が重い空気を和ませる(笑わせにくる)ため、重いテーマながら読みやすい。
自分を好きになれる一冊です。
1983年東京都生まれ。2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞し、デビュー。同作品で04年に第130回芥川賞を受賞。10年『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞を、12年『マザーズ』で第22回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を、20年『アタラクシア』で第5回渡辺淳一文学賞を、21年『アンソーシャルディスタンス』で第57回谷崎潤一郎賞を、22年『ミーツ・ザ・ワールド』で第35回柴田錬三郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)
黒猫(ポー傑作選1 ゴシックホラー編 ) エドガー・アラン・ポー
1809-1849年。推理小説の創始者、ゴシックホラー小説やSF小説の先駆者とも言われるアメリカの小説家、詩人、雑誌編集者。極めて知的に多様なジャンルの物語を紡ぐストーリーテラーであると同時に、音楽性に優れた詩人であり、「大鴉」は生前大ヒットしてポーの仇名にもなった。ボードレールらフランス象徴派詩人や、ジュール・ヴェルヌら後代のSF作家らに与えた影響は大きい。その生涯も謎に満ちており、まさにミステリーを体現した作家といえる(「BOOK」データベースより)