「愛が、人に正しいことだけをさせるものであればいいのに。」
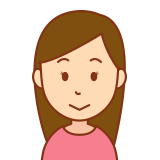
こんにちは、くまりすです。今回は、新聞、週刊誌各誌で大反響の問題作、モデルに書かれた瀬戸内寂聴さん絶賛の井上荒野「あちらにいる鬼」をご紹介いたします。
story
1966年、講演旅行をきっかけに男女の仲となる二人の作家ー白木篤郎と長内みはる。繰り返される情事に気づきながらも心を乱さない篤郎の美しい妻、笙子。愛と“書くこと”に貫かれた人間たちの生を描ききった傑作。至高の情愛に終わりはあるのか?(「BOOK」データベースより)
恋人と妻
妻子ある小説家の白木篤郎と出会った長内みはる。次第に彼に惹かれていったみはるは恋人と別れ、白木と逢瀬を重ねてゆく。一方、妻の笙子はみはるの存在に気づきつつも、その日常を受け入れていた…
この小説は、白木の恋人のみはると篤郎の妻の笙子の奇妙な三角関係を、それぞれの視点で描いています。時間の経過と共に物語が進行するので、夫や恋人への気持ちの変化や本音が垣間見えて、彼女たちの愛の自叙伝のようにも読むことが出来る。
「なれなれしい男だと思ったが、どこか私ではなく、空中に空いた穴に向かって喋っているようでもあった。」
「結局彼の方が人形師の心をとらえてしまった。白木は子供のように目を輝かせ、(中略)目の前の相手に掛け値なしの敬意や憧憬が溢れていた。」
女心や母性本能をくすぐる男、いわゆるモテる要素を兼ね備えたという男というのはこういう男の事をいうのだろうなと頷かせるくらい、白木篤郎の魅力が二人の女性の語りから伝わってくる。
一人の男を好きになっていく表現に女心が揺さぶられます。
「いつものことだが、少し不思議な気持ちで、そして少し憂鬱にもなって、夫の顔を眺めた。篤郎は仕方のない嘘吐きだが、こういうときの興奮や怒りだけは本物なのだ。それは彼という男の最悪な所でもある。砂は砂だけでできていればいいのに。」
女が男を愛した時、愛された時に感じる幸せや安心感、そして嫉妬や不安。その告白の比喩と、的確な言葉のバランスが絶妙で、白木篤郎に対する想いが手に取るように伝わってきます。
本音が見え隠れしながらも、決してドロドロした暗い雰囲気にはなってなく、強さや情熱がある一方で、冷めた部分ものぞかせる女性の複雑な胸の内が赤裸々に表現されている。
実話?
この物語は、著者の父の井上光晴、瀬戸内寂聴、そして著者の母をモデルとして描かれたものだそうです。
著者が長年見てきた家族をもとに描かれていて、みはるのモデルとなる寂聴に取材を重ねたのだとか。一方、笙子のモデルの著者の母親については、彼女の言動を思い出しながら想像で書いたとのこと。
「この三人の事実を書いたわけではなくて、私にとっての、この三人の真実を書いたんだなって思います。」
事実は誰が見ても変わらないものだけれど、真実は人によって変わる。
みはるや笙子が普通の感覚とはちょっと違う思考や行動は、愛の形が千差万別なように二人にとっての真実がきっとあったのだと思います。
「モデルに書かれた私が読み傑作だと、感動した名作!!」「作者の未来は、いっそうの輝きにみちている。百も千もおめでとう」と、瀬戸内寂聴さんも大絶賛されている本作品。
ノンフィクション部分もかなり盛り込まれているんじゃないかと想像を掻きたてられますね。

感想
「女性は愛される方が幸せになる」なんて言いますよね。それは、経験則や周りの人からの情報によって、統計的にそうだと結論付けられるそうです。
女性が集まると盛り上がるのはやっぱり恋愛話で、女性の大きなの関心事の一つですね。その時代によって、「花より団子」、「世界の中心で、愛を叫ぶ」などのドラマや映画、漫画で誰もが知っている作品も多数あります。不倫に関するものも「マディソン郡の橋」、「東京タワー」、「昼顔」パッと思い出すだけでもこれだけありました。
不倫をしようと意気込んでいる女性はあまりいないと思いますが、そこまで出来る「愛」ってどんなものだろうという興味や、運命の人に出会いたいという願望を持っている人は多いと思います。ですから、その疑似体験が出来る映画や小説も人気が出るのですね。
この小説の面白いところは、その愛の炎が燃え上がった瞬間だけでなく、恋が芽生えた瞬間から生涯を通して描かれているところで、運命の人に出会った女性の一生を疑似体験することが出来ました。
1961年東京都生まれ。89年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2004年『潤一』で島清恋愛文学賞、08年『切羽へ』で直木賞、11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、16年『赤へ』で柴田錬三郎賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞受賞(「BOOK」データベースより)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)



